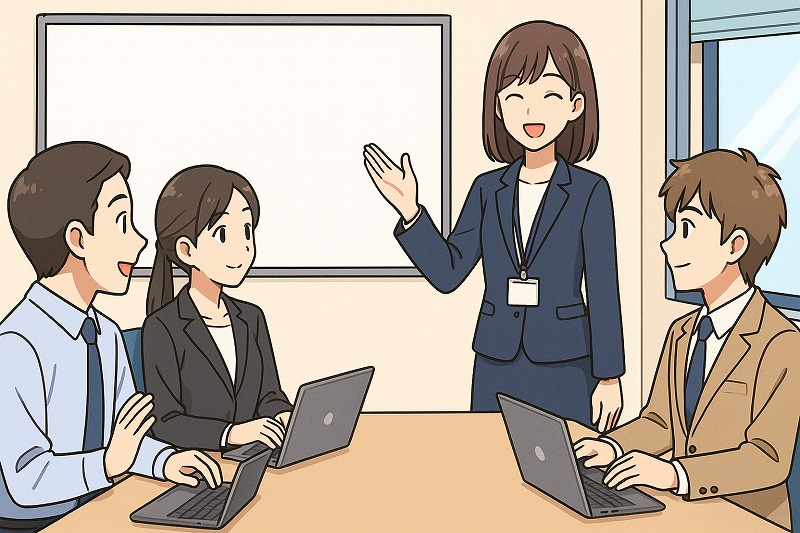会議の場では、司会進行を担当する人にとって「何をどう話せばよいのか」に悩むことが少なくありません。特に初めて司会を任された場合、緊張や不安で頭が真っ白になってしまうこともあるでしょう。そんなとき、実際に使える例文を知っておくと、安心して会議を進められるようになります。
本記事では、会議の冒頭あいさつから議題の説明、中間のまとめ、そして終了時のしめくくりまで、司会進行に必要な例文を場面ごとに紹介しています。社内会議・社外会議・オンライン会議など、さまざまなシーンに対応できる内容をそろえており、言葉の選び方や話し方のコツも盛り込んでいます。
スムーズで信頼感のある司会進行は、会議全体の印象や成果にも大きく影響します。この記事を通じて、実用的な例文を参考にしながら、自分らしい進行スタイルを身につけていきましょう。
- 会議の司会進行に使える具体的な例文
- 会議開始から終了までの話し方の流れ
- 場面や相手に応じた言葉遣い
- 会議を円滑に進めるための基本的なポイント
会議の司会進行に使える例文まとめ

●目的とゴールを伝える例文
●議題と時間配分を説明する例文
●自己紹介を含めた司会進行の例文
●社外向けの丁寧なあいさつ例文
●会議ルールを共有するための例文
会議開始時の基本的な司会あいさつ例文
会議を始める際は、参加者に対して感謝の気持ちを伝えつつ、これから始まる議題への集中を促すことが大切です。会議の冒頭は参加者の意識を切り替えるタイミングでもあり、メリハリのある一言が必要です。
例文①:社内の定例会議向け(カジュアルかつ丁寧)
例文②:初対面の多い会議・プロジェクトキックオフ向け(少し丁寧なトーン)
例文③:社外の参加者を含む正式な会議向け(フォーマルで丁寧)
このように挨拶の中には、「時間が来たこと」「参加への感謝」「自己紹介」「意気込み」を含めると、自然で丁寧な印象を与えられます。スムーズな開始の挨拶ができれば、その後の進行も落ち着いて行いやすくなります。
目的とゴールを伝える例文
会議の初めに目的とゴールを明確に伝えることで、参加者の意識がそろい、議論が効率的になります。何のために集まっているのかがはっきりすることで、話が逸れにくくなるからです。
例文①:進捗確認や情報共有を目的とする会議向け
例文②:意思決定を目的とした会議向け
例文③:複数部署が関わる企画会議向け
この文では、「何について話し合うのか」と「最終的にどうなれば良いか」がはっきりしています。参加者が自分の役割や発言の方向性をつかみやすくなる点がメリットです。
議題と時間配分を説明する例文
会議中に議論が長引かないようにするには、あらかじめ議題とそれぞれの時間配分を共有しておくことが有効です。時間の見通しを持つことで、参加者は発言の優先度を判断しやすくなります。
例文①:シンプルな定例会議向け
例文②:社外との合同会議など、丁寧に伝える場面向け
例文③:柔軟な対応を前提としたフレキシブルな会議向け
このように伝えると、参加者は今どこにいるのかを常に意識しながら議論できます。また、時間管理を意識して発言が簡潔になりやすいという利点もあります。時間配分の説明は、円滑な会議運営に欠かせない要素の一つです。
自己紹介を含めた司会進行の例文
初対面の参加者が含まれる会議では、司会者が自己紹介を行うことで安心感や信頼感を生み出すことができます。誰が進行役なのかを明らかにすることで、会議の雰囲気も整いやすくなります。
例文①:社内の少人数会議向け(カジュアル)
例文②:部署をまたぐ社内会議向け(丁寧)
例文③:社外の参加者がいる会議向け(フォーマル)
この文では、挨拶・感謝・自己紹介・進行役としての姿勢を一文ずつ丁寧に述べています。これにより、参加者は安心して会議に参加しやすくなります。自己紹介は単なる名前の紹介ではなく、会議を円滑に進めるための準備の一つと考えましょう。
社外向けの丁寧なあいさつ例文
社外の関係者が出席する会議では、より丁寧な言葉遣いや気配りが求められます。冒頭のあいさつで印象を損ねてしまうと、会議全体の雰囲気にも影響が出ることがあります。
例文①:初めての会議や打ち合わせの冒頭
例文②:定期的な打ち合わせや進捗確認の会議
例文③:複数の社外関係者が集まる合同会議などでのあいさつ
この例では、言葉遣いを柔らかくしつつも、丁寧さを保ったあいさつとなっています。「誠に」「どうぞよろしくお願い申し上げます」といった表現が、社外向けの敬意を示すポイントです。初対面の印象を良くするためにも、丁寧なあいさつは非常に重要です。
会議ルールを共有するための例文
会議の効率を高めるためには、事前にルールを共有しておくことが効果的です。特に参加者が多い場合や自由な発言が求められる会議では、共通のルールがないと議論が混乱しやすくなります。
例文①:少人数の社内会議向け(基本的なルール)
例文②:オンライン会議向け(テクニカル面にも言及)
例文③:社外との合同会議向け(丁寧で明文化されたルール)
このように箇条書きで伝えると、参加者も理解しやすくなります。また、ルールを事前に資料として配布しておくと、当日の混乱も少なくなります。ルールを共有することは、全員が安心して参加できる会議の土台づくりとも言えます。
会議を円滑にする司会進行の例文

●意見が対立した際の切り返し例文
●会議の中間まとめの例文
●決定事項のまとめ方の例文
●終了時に使えるあいさつ例文
議論が脱線した時の例文
会議中に話題が本来の議題から逸れることはよくあります。そうした場面では、進行役がやんわりと軌道修正することが求められます。参加者に不快感を与えずに話を戻すには、表現やタイミングに配慮が必要です。
例文①:やんわりと話を戻す場合
例文②:今の意見を評価しつつも次に進めたい場合
例文③:時間を意識して切り替える場合
このように「一度戻す」という表現を使うと、否定的な印象を与えずに軌道修正が可能です。話を戻す際は、感謝や共感の言葉を添えると、指摘がやわらかく伝わります。
意見が対立した際の切り返し例文
会議では異なる立場からの意見がぶつかることがあります。対立自体は悪いことではありませんが、そのまま放置してしまうと雰囲気が険悪になり、生産的な議論ができなくなります。そんなときは、場の空気を和らげつつ、冷静な対話の流れをつくる発言が求められます。
例文①:両者の意見を肯定しつつ整理する場合
例文②:対立を前向きにとらえて次に進める場合
例文③:冷静さを保つよう促す場合
意見がぶつかる場面では、片方の意見だけを重視すると場の空気が悪くなる可能性があります。中立の姿勢を保ち、対話を続ける前向きな姿勢を示すことで、会議全体の雰囲気も安定しやすくなります。
会議の中間まとめの例文
会議の途中で議論が一通り終わった段階では、進行役が中間的なまとめを行うと、参加者の理解が深まり次のステップに進みやすくなります。話が多岐にわたるほど、中間での整理は重要です。
例文①:進捗確認の途中で整理する場合
例文②:意見が出そろったあとに共通点を整理する場合
例文③:時間を意識しつつ次に進むための切り替え例
中間まとめでは、「今どこまで話が進んでいるか」「何が決まり、何が保留か」を明確に伝えることが大切です。会議の流れを整える役割として、適切なタイミングで取り入れていきましょう。
決定事項のまとめ方の例文
会議の終盤では、話し合われた内容を明確に整理し、参加者全員が同じ認識を持てるようにする必要があります。決定事項のまとめ方があいまいだと、あとで認識違いや作業漏れが起きてしまうこともあります。
例文①:簡潔に箇条書きで整理する場合
1点目、〇〇の導入は来月から開始すること。
2点目、□□に関する対応は△△さんが担当すること。
3点目、次回の会議は〇月〇日に実施すること。
以上でよろしいでしょうか?」
例文②:社外の参加者がいる場面で丁寧に伝える場合
まず、〇〇についてはA案を採用する方向で一致いたしました。次に、□□の対応については、双方で再度検討し、来週中に最終案を共有することになりました。その他の点については、次回会議で継続協議となります。何か追加や訂正がございましたら、お知らせください。」
例文③:議論が複雑だった場合に要点を整理する形
・〇〇の改善策は試験的に1か月実施。
・定例報告のフォーマットは新案に統一。
・△△の対応は引き続き検討、次回再確認。
以上3点が本日の決定・確認事項です。」
決定事項を明確に伝えることで、「何を」「誰が」「いつまでに」という実行ベースの理解が得られます。決定事項の伝え方は、会議の成果を形にする最後のひと押しです。丁寧かつ簡潔に伝えるよう意識しましょう。
終了時に使えるあいさつ例文
会議の締めくくりでは、内容の総括とともに、参加への感謝を述べることで良い印象を残すことができます。ただ終わらせるだけでなく、参加者に「意味のある会議だった」と感じてもらえるようにすることが大切です。
例文①:社内の定例会議や短時間の会議向け(シンプル)
例文②:プロジェクト関連の会議や社外との打ち合わせ向け(やや丁寧)
例文③:複数の関係者が出席する正式な会議向け(フォーマル)
終了時のあいさつでは、「感謝」「まとめ」「次の行動」を意識すると自然で信頼感のある印象を与えることができます。また、時間ぴったりで終わることが難しい場合でも、きちんと締めの言葉を用意しておくと会議の印象が整います。
会議の司会進行に役立つ例文まとめ
会議を円滑に進めるためには、的確な司会進行が欠かせません。特に冒頭のあいさつや自己紹介、目的や議題の説明、ルールの共有などは、会議の流れと空気感を左右します。
今回の例文集では、会議開始時の基本的なあいさつから、議題と時間配分の提示、対立意見への対応、終了時のしめくくりに至るまで、あらゆる場面に対応できる司会進行の例文を紹介しています。
形式や参加者の立場(社内・社外)に応じて、トーンや言葉選びを調整することが重要です。例文をそのまま読むのではなく、あくまでベースとして活用し、自分の言葉に置き換えることで自然な進行につながります。
これらの例文は、会議初心者だけでなく、慣れている方にとっても、場面に応じた言い回しの引き出しとして役立つ内容です。会議の司会進行に自信を持つための参考として、ぜひ活用してください。