研修を受けた後にレポートを書く場面は多くありますが、「どのようにまとめればよいのか」「何を書けばいいのか」で悩む方は少なくありません。特に、新人研修・中堅社員研修・リーダー研修など、研修の種類によって内容や視点も異なり、それぞれに合った書き方が求められます。
本記事では、「研修で学んだこと」を的確に伝えるための例文を豊富にご紹介します。新人からリーダー層まで幅広く使える実例をもとに、読みやすく、説得力のあるレポートの書き方を解説しています。また、レポートの書き出しに迷ったときの文例や、締めとして使いやすいまとめの一文も掲載しており、全体の構成を整えたい方にも役立つ内容です。
記事を通して、研修の学びを効果的に文章化するためのヒントをお伝えしていきます。
- 研修で学んだことを的確にまとめたレポートの書き方
- 新人研修・中堅社員研修・リーダー研修それぞれの例文
- 書き出しや締めに使えるレポート文の具体例
- 読みやすく伝わるレポート構成と文章の工夫
研修で学んだことをレポートに書く例文集
●中堅社員研修で使えるレポート例文
●リーダー研修の例文
●感想文形式のレポート例文
新人研修レポートの例文
新人研修では、ビジネスマナーや社内ルール、業務の基本的な流れについて学ぶことが一般的です。以下は、実際にレポートで使える例文です。
例文1:研修の概要に触れる書き出し
今回の新人研修では、
社会人としての基本的なマナーや仕事の進め方について学びました。
初めての経験ばかりで戸惑うこともありましたが、
実践的な内容を通して多くの気づきを得ることができました。
例文2:研修内容に対する具体的な感想
特に印象に残っているのは「報連相(報告・連絡・相談)」の重要性です。
職場での信頼関係を築くうえで、
相手に適切なタイミングで情報を伝えることの大切さを改めて感じました。
例文3:自分の課題に気づいた点を述べる文
研修を通じて、自分には主体的に動く姿勢がまだ不足していると実感しました。
指示を待つのではなく、状況を見て自ら行動することの必要性を強く認識しました。
例文4:今後の行動目標に関するまとめ
今後は、今回学んだ内容を日々の業務に活かし、
職場で信頼される存在を目指していきます。
特に、時間管理や報告の正確さを意識しながら行動していきたいと考えています。
例文5:全体を締めくくる結びの言葉
今回の新人研修で得た学びを大切にし、
今後の業務に前向きな姿勢で取り組んでいきます。
まだ分からないことも多いですが、
一つずつ丁寧に吸収しながら成長していきたいと思います。
このように、自身が印象に残った内容や、それが今後の業務にどう活かされるかまで述べると、説得力のある文章になります。
一方で、抽象的な表現に終始すると伝わりにくくなります。「マナーを学びました」だけではなく、どのようなマナーだったのか具体的に記すと読み手の理解も深まります。
中堅社員研修で使えるレポート例文

中堅社員研修では、後輩指導や業務改善に関するテーマが中心になります。そのため、レポートにも「実務への応用」や「課題発見力」などが求められます。
例文1:自分の立場を意識した書き出し文
今回の中堅社員研修では、自分の業務だけでなく
周囲との関わり方や組織全体を見渡す視点の重要性について学びました。
これまでの経験を振り返るよい機会となりました。
例文2:業務改善の視点での気づき
研修の中で取り上げられた「業務の見える化」
というテーマは非常に印象に残りました。
日々の業務に無意識のうちに無駄が発生していることに気づき、
今後は優先順位の明確化とタスクの共有を意識したいと感じました。
例文3:チームへの影響を考えた内容
中堅社員として、チームの雰囲気づくりや後輩の育成にも
関心を持つべきだと強く感じました。
自分一人で完結する仕事の進め方から、
周囲の状況に目を配る意識へと変化が求められていると実感しました。
例文4:今後の働き方の目標を示す文
今後は「自ら考え、周囲を巻き込みながら動く」ことを意識し、
組織にとってプラスになる行動を積極的に取っていきたいと思います。
また、後輩や新人への助言も怠らず、
学びを共有できる環境づくりにも努めます。
例文5:全体のまとめとしての結び文
中堅という立場は、現場と管理層の橋渡し的な存在でもあります。
今回の研修を通して、その役割の重要性と責任の重さを再確認しました。
今後も組織の一員として、成長し続けられるよう日々努力していきます。
このように、研修内容と自分の業務を結びつけて記述すると説得力が増します。
ただし、「改善できそうだと感じた」といった曖昧な表現ではなく、どのように活かす予定かを簡潔に述べることが重要です。例えば「次回の会議では、ワークで学んだ整理法を試してみたい」といった表現が効果的です。
リーダー研修の例文

リーダー研修では、組織運営やメンバーの育成に関する内容が中心です。ここでは、部下との関わり方や、指導方法についての気づきをまとめるのがポイントになります。
例文1:リーダーの役割を見つめ直した気づき
今回のリーダー研修を通じて、リーダーとは指示を出す人ではなく、
メンバーの力を引き出す存在であるという考えに共感しました。
これまでの自分の関わり方を見直すきっかけとなりました。
例文2:実際の現場と照らし合わせた学び
研修で学んだ「傾聴力」の重要性は、
チーム内でのコミュニケーション改善にも直結すると感じました。
普段の業務においても、
部下の声に真摯に耳を傾ける姿勢を心がけたいと思います。
例文3:リーダーとしての課題意識を明文化
私自身、これまで部下へのフィードバックが少なかったことを反省しました。
今後は定期的な対話の場を設けることで、
個々の成長とチームの一体感につなげたいと考えています。
例文4:研修内容を行動に落とし込む宣言文
リーダーシップを発揮するには、
自分自身の感情をコントロールする力も求められると学びました。
焦らず、冷静に状況を判断するためにも、
日頃から振り返りの習慣を持ちたいと思います。
例文5:今後の展望を含めたまとめ文
リーダーとしての在り方を改めて考える貴重な研修でした。
チームの成果を最大化するためには、
一人ひとりと向き合う姿勢が不可欠です。
今回得た知見を日々の業務に活かし、
信頼される存在を目指します。
このように、「何を学び」「どう変えるか」を明確にすると、読み手に意図が伝わりやすくなります。
よく使われる表現としては「~の重要性を再認識した」「~する意識が高まった」などがありますが、頻繁に使い過ぎると内容が薄く見えてしまいます。必要に応じて別の言い回しにすることも検討しましょう。
感想文形式のレポート例文
感想文形式のレポートでは、研修を通じて感じたことや気づきを自分の言葉で表現することが重要です。事実の羅列ではなく、主観を含めた感想を中心に構成しましょう。
例えば次のような例文が参考になります。
「今回の研修を受け、自分の考え方がいかに一方的であったかに気づかされました。特に、他部署との連携の大切さについての講義は印象的で、普段の業務の中でも視野を広く持つことが求められていると感じました。」
このように、自身の内面の変化や新たな視点を取り入れた表現が好まれます。また、「印象に残った内容」と「なぜそう感じたのか」をセットで記述すると、読み手の理解を助けます。
ただし、感情の表現が曖昧にならないよう注意が必要です。「勉強になりました」「参考になりました」だけでは具体性が不足します。何がどのように役立ったかを明確にすると、説得力のある文章になります。
研修で学んだことをレポートにする例文と書き方のコツ

●内容を整理しやすい書き方の流れ
●締めに使えるまとめの例文集
●書き方の基本ルールと注意点
●わかりやすい文章にする構成の工夫
●自分の学びを的確に伝えるポイント
●読み手に伝わる文章の書き方
レポートの書き出しで迷わない方法
レポートの書き出しでは、読み手にテーマや目的を明確に伝えることが重要です。初めてレポートを書く人は、いきなり内容を書き始めようとして筆が止まることが多くあります。そんなときは、まず「いつ・どこで・何を学んだのか」といった事実から書き始めるとスムーズです。
例文1:研修全体の印象から入る書き出し
今回の研修を通じて、自分自身の考え方や行動に対して
多くの気づきを得ることができました。
特に印象的だったのは、
日々の業務に対する向き合い方についての内容です。
例文2:研修参加前の心境からスタートする書き出し
正直なところ、研修前はどのような内容なのか不安もありましたが、
実際に参加してみると、業務に直結する学びが多く、
大変有意義な時間となりました。
例文3:学んだテーマの紹介から始める書き出し
今回の研修では「リーダーシップ」や「コミュニケーション」
に関する内容が中心となっており、現場での役割を再確認する機会となりました。
例文4:問題意識に触れる書き出し
これまでの自分の業務の進め方に対して、
どこか物足りなさを感じていました。
今回の研修では、
その原因を明確にするヒントを得ることができました。
例文5:今後の変化を示唆する導入
研修で得た学びをきっかけに、
今後の働き方を見直す必要があると強く感じました。
本レポートでは、学んだ内容と今後の行動について整理します。
このように、時系列や研修の概要を簡潔に記述することで、全体の流れをつかみやすくなります。書き始めに「目的」や「受講理由」を一文添えると、さらに読みやすい導入になります。
また、主語が自分(私は〜)で始まると文章が安定しやすいため、不安な場合はまず自分の視点から書くことを意識しましょう。書き出しで無理に印象的な言葉を使おうとせず、丁寧に事実から記述することが読み手への配慮にもつながります。
内容を整理しやすい書き方の流れ
レポートをスムーズにまとめるには、全体の構成をあらかじめイメージしてから書くことが効果的です。無計画に書き進めてしまうと、話題が前後してわかりにくくなってしまいます。
1. 全体構成を決める
まず最初に、レポート全体の「型」を決めておくと、書き進める際に迷いが少なくなります。以下のような流れが基本です。
- 書き出し(導入)
研修のテーマや目的、参加した経緯などを簡潔に説明します。 - 主な内容
研修で取り上げられたテーマや印象に残った点を整理して書きます。 - 学び・気づき
自分が何を学び、どのような変化や発見があったかを明確に伝えます。 - 今後の活かし方・まとめ(締め)
学びを今後どのように活かすか、または全体の感想をまとめて締めます。
2. 段落ごとに役割をもたせる
文章全体が読みにくくなる原因の一つに、「一文・一段落の中に複数の話題を入れてしまう」ことがあります。そこで、各段落には以下のように明確な役割をもたせます。
- 第一段落:研修の概要
- 第二段落:印象に残った場面や話
- 第三段落:自分の気づきや意識の変化
- 第四段落:今後どう行動に移すか
このように整理することで、読み手は文章の流れを自然に追うことができ、内容を正確に理解しやすくなります。
3. 見出しや箇条書きで視覚的にも整理
必要に応じて、簡単な小見出しや箇条書きを使うと、内容を視覚的に整理しやすくなります。特に、「学びのポイント」や「印象に残った言葉」などを列挙したい場合には、箇条書きが有効です。
例:
- 講師が強調していた「〇〇の重要性」
- グループワークで実感した「△△の難しさ」
- 自分に不足していた「□□の視点」
4. つなぎ言葉で滑らかな文章にする
段落や文と文の間に、適切な接続語やつなぎの表現を入れると、文章全体が滑らかになります。例としては以下のような言い回しが効果的です。
- そこで私は〜
- このとき特に感じたのは〜
- また、印象的だったのは〜
- このような経験から〜
このような表現を使うことで、ただの「出来事の羅列」ではなく、考察が加わった整理された内容に仕上がります。
一度、箇条書きでメモを作成してから本文を書くのも有効です。頭の中が整理され、無駄のない構成になります。
締めに使えるまとめの例文集
レポートの締めは、全体をきちんと振り返り、今後への意欲や行動につなげる言葉で終えるのが理想です。ここで印象に残る一文があると、読み手にも強く伝わります。
例文1:今後の行動目標で締めくくる
今回の研修で得た気づきを日々の業務に生かし、
今後も成長を続けられるよう意識して行動していきます。
例文2:感謝と意欲を込めて終える
このような学びの機会をいただいたことに感謝し、
研修で学んだことを業務の中で実践していきたいと思います。
例文3:学びの再確認でまとめる
今回の研修を通じて、
業務への姿勢やチームで働く意義を改めて考えることができました。
これらの学びを今後にしっかりつなげていきます。
例文4:研修の価値を強調して締める
限られた時間の中で多くの学びを得られたことは、
私にとって大きな財産となりました。
今後も成長を止めず、より良い成果につなげていきます。
例文5:自己評価と前向きな言葉で終わる
自分の課題と向き合いながらも、
新たな視点を得ることができた研修でした。
この経験を大切にし、次のステップへと進んでいきます。
このように、今後の姿勢や行動目標を明記することで、レポートに前向きな印象を残すことができます。
一方で、あいまいな意気込みで終わってしまうと説得力に欠けます。例えば「がんばりたいと思います」だけでは抽象的すぎるため、「○○を意識して取り組みます」と具体的に締めくくる工夫が求められます。
書き方の基本ルールと注意点
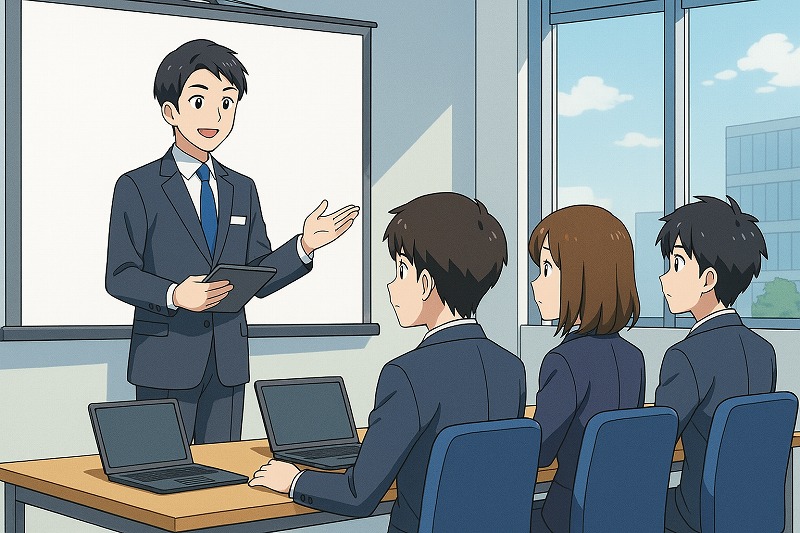
レポートを書く際には、いくつかの基本的なルールと注意点を守ることが求められます。まず、文字数や提出形式など、指定された条件を必ず確認しましょう。これを怠ると、どれだけ内容が良くても評価が下がる可能性があります。
文体は「です・ます調」で統一し、読みやすさを意識します。改行の間隔や段落分けにも配慮し、視覚的にも整理された文章にすることが大切です。
注意したいのは、主観と客観を混同しないことです。「私は〜と思いました」という感想と、「研修では〜が解説されました」という事実は区別して記述しましょう。さらに、抽象的な表現や曖昧な言い回しも避け、なるべく具体的なエピソードや事例を挙げることで、読み手に理解されやすい内容になります。
また、誤字脱字のチェックは必須です。書き終えたら一度声に出して読んでみると、不自然な部分に気づきやすくなります。丁寧な仕上げが信頼感にもつながるため、最後まで気を抜かないようにしましょう。
わかりやすい文章にする構成の工夫
文章をわかりやすくするには、構成をシンプルかつ明確にすることが重要です。読み手が内容をすぐに理解できるよう、文章全体の流れを整える工夫が求められます。
まず意識したいのは「一段落に一つの話題」を守ることです。一つの段落に複数のテーマを詰め込んでしまうと、内容が散らかり読みにくくなります。特にレポートでは、「研修内容」「気づき」「活かし方」など、要素ごとに区切って書くと伝わりやすくなります。
また、接続詞を適切に使うことで文と文のつながりを滑らかにし、論理的な構成ができます。例えば「その結果」「しかし」「このように」などを効果的に入れることで、読者の理解を助ける流れができます。
さらに、最初に概要、次に具体例、最後にまとめという順番を意識すれば、自然と読みやすい構成になります。全体の文字数に余裕がある場合は見出しを加えると、視覚的にも整理されて読者の集中力を保ちやすくなります。
自分の学びを的確に伝えるポイント
研修レポートでは、ただ学んだ内容を羅列するだけでは読み手に印象を与えることができません。大切なのは、自分なりの気づきや変化を具体的に伝えることです。
まずは「どの場面で、何に気づいたのか」を明確にすることで、個人の視点がはっきりと伝わります。「講師の説明を聞いて初めて〇〇の大切さに気づいた」といった一文が入るだけでも、自分の学びが生きたものとして伝わります。
また、自分の経験や業務との関連性を言及すると、内容に説得力が増します。たとえば、「これまでの業務では意識していなかったが、今後は〇〇を取り入れてみたい」と書けば、実践に結びつけた学びとして伝えられます。
注意したいのは、抽象的な表現を避けることです。「勉強になりました」や「参考になりました」などは印象がぼやけてしまいます。できるだけ具体的な表現を使い、自分自身の変化や行動につながる形で書くことが的確に伝えるコツです。
読み手に伝わる文章の書き方
読み手に伝わる文章を書くためには、読みやすさと論理性を意識する必要があります。ただ正しい日本語を書くというだけでは不十分で、伝えたいことを明確にし、過不足のない表現を心がけることが大切です。
まず、主語と述語を対応させるなど、文法上の基本を守ることが前提です。そのうえで、一文が長くなりすぎないよう、適度に句読点を打つことを意識しましょう。読点が少ないと、読む側が息継ぎできず、理解しにくくなります。
さらに、誰に向けて書いているのかを常に意識しておくと、言葉選びや説明の丁寧さが変わってきます。例えば、専門用語を使う場合は簡単な言い換えや補足を添えることで、読む人の理解度が高まります。
最後に、読んだ人が「なるほど」「わかりやすい」と感じるためには、文章の流れに無理がないことが大切です。不自然な話題の切り替えや、飛躍した結論になっていないか、全体を見直す時間を取ることをおすすめします。文章力は一度で完璧になるものではありませんが、丁寧に書き上げる姿勢が伝わる文は、必ず読み手に響きます。
研修で学んだことをレポートに書く例文まとめ
研修で学んだことを的確にレポートにまとめるには、目的や内容、気づき、今後の行動といった要素をバランスよく記述することが重要です。
たとえば、新人研修ではビジネスマナーや基本動作の理解を中心に書き、中堅社員研修では業務改善や後輩指導の視点を取り入れます。リーダー研修では、部下との関係性やチームの方向性に対する気づきを含めると説得力が増します。
例文を活用する際は、ただコピーするのではなく、自分の経験と照らし合わせて調整することがポイントです。感想文形式であれば、率直な心の動きや学びへの気づきを軸に据えると、読み手の共感を得やすくなります。
どの形式でも、締めくくりには今後の行動目標や感謝の気持ちを添えることで、前向きな印象を与える文章になります。研修で学んだことを振り返り、自分の言葉で伝える姿勢が最も大切です。


